久しぶりに朗読が聞きたくなり、YouTubeで青空文庫の朗読を漁っていました。
芥川龍之介の文章の朗読をいろいろ聞いたのでその感想メモです。
ちなみにこちらの朗読プレイリストから視聴しています。
- 大きな鼻を持つ男が劣等感に苦しむ「鼻」
- 悪魔の歪んだ愛情とは「悪魔」
- 煙草をもたらした悪魔の架空伝説「煙草と悪魔」
- 人の思い込みに関するちょっと不思議な話「貉」
- 怪物も幽霊も出てこないけれど嫌な気分になる「妙な話」
- エンタメっぽい俗っぽさ「アグニの神」
- 犬が黒犬になって大冒険「白」
- カフェの女給の恋における一抹の日常「葱」
- 仙人に弟子入りした男の価値観「杜子春」
- 人を見た目で判断しているのに何かいい話っぽくなっている「蜜柑」
大きな鼻を持つ男が劣等感に苦しむ「鼻」
巨大な鼻を持つ僧侶が劣等感に苦しむ話。
見た目に悩みがある、しかし、その見た目の悩みを解決したところで救いは現れない、というルッキズムの話でした。
人と鼻の大きさが違うというだけで世の中からの疎外感に悩まされ、うつうつとしている下りは心理描写にリアリティがありました。
いつも鼻のことを考えたり、自分が鼻を気にしているから他人の鼻をやたらと気にしてしまったり、今でもあるある……と思える内容です。
作品の途中で主人公は(比較的)普通の鼻を得ますが、それでも外見の問題は解決しないところが皮肉でした。
現実でも、ダイエットに成功したのに劣等感にとらわれたり、整形したのに自分の外見を受け入れることができず何度も整形を繰り返したり、この作品に通じる悩みがあります。
ラストシーンはどう受け取っていいのか悩みましたが、主人公が最初より幸せそうなところはよかったです。身も蓋もない話ですが、「開き直る」が一番の解決策なのかもしれません。
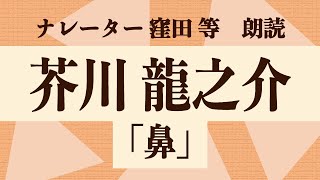
悪魔の歪んだ愛情とは「悪魔」
とある悪魔が生々しい胸の内を告白する話。
ヨーロッパが専門だった身としてはだいぶキリスト教への思想が偏っていると感じますが、フィクションとしては面白かったです。
美しく穢れないものほど堕落させたい、という悪魔の告白は、倫理のないフィクションを書いてしまう身としてはわかるものがあります。
見えざるものを見る聖職者に悪魔が心の内を明かす、という単純な話ですが、歪んだ愛情や美しいものへの劣等感が感じられる話でした。
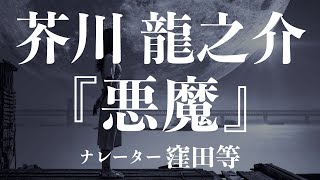
煙草をもたらした悪魔の架空伝説「煙草と悪魔」
日本に煙草を持ち込んだ悪魔の話。架空昔話。
「イエス・キリストもたくさんいる神のひとつ」と思っているところがやはりものすごく日本人的ですね。
悪魔がやることがないという理由で突然ガーデニングを始め煙草を育てるところに笑ってしまいました。人間味のある悪魔です。
わかりやすい創作昔話ですが、悪魔が正体を現すところや、牛商人が悪魔の畑に忍び込むところに非常に臨場感があって面白いです。
とんち話のようなオチなので、普段あまり本を読まない人にも読みやすい部類だと思います。

人の思い込みに関するちょっと不思議な話「貉」
貉(むじな)が人を化かすことについて語る。ちょっと不思議な話です。
人の言葉はどこから創作でどこから怪異なのか? と認識の違いについて考えさせられる話です。
案外伝説や伝承というものはこういう何気ない嘘から始まるのかもしれません。
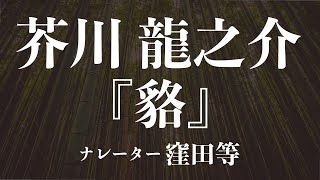
怪物も幽霊も出てこないけれど嫌な気分になる「妙な話」
知らないはずのことを知っている不思議な赤帽の話。
幽霊や怪物が出てくるわけではないのですが、うっすら不安になってくるような怪異小説です。
同じ顔のはずなのに思い出せない、そして他の人に紛れると区別がつかないという単純だけれど生々しい怖さがあります。
怪談話として聞いていたら最後の2,3行にええ? となりました。性格の悪い終わり方です。
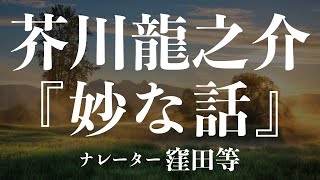
エンタメっぽい俗っぽさ「アグニの神」
怪しげなインド人のおばあさんから神がかりになる女性を助ける話。
インドには詳しくないけれど絶対インドの信仰ってこんなものじゃないでしょう!? とツッコみたくなりました。
文学というより怪奇小説っぽい内容で、エンタメ色が強いです。男がかわいそうな女性を救うところもそうですしね。
TRPGのシナリオにこういうのがありそうです。
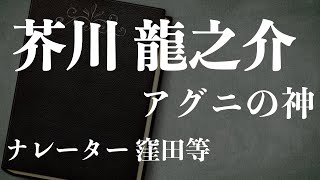
犬が黒犬になって大冒険「白」
犬の白がいろいろあって大冒険をする話。
話の展開にはうーん? ちょっと変では? となる部分もありますが、とにかく犬が健気でかわいいです。犬が好きな人には泣けるかもしれません。
白の心理描写が丁寧でした。飼われている家の子どもたちに気づいてもらえなくてショックを受けるシーンには心が苦しくなりました。
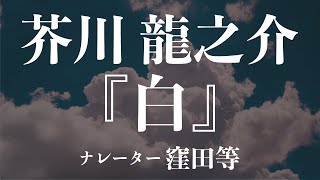
カフェの女給の恋における一抹の日常「葱」
突然作者である「おれ」が語り出したり口をはさんだりするというメタ作品。昔の作品って自由ですね。
昔のカフェの女給はホステスみたいなもので、水商売の一種だったということがわかる内容です。
芸術的なものにあこがれるお君さんが、安売りのねぎの束で突然現実に引き戻され、普通の女になってしまうところが面白かったです。
でもキラキラしたものにあこがれる人ってそういうものな気がします。やっぱり現実からは抜けきれない。
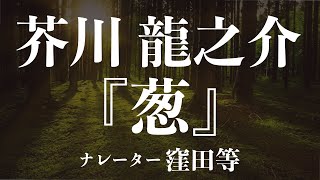
仙人に弟子入りした男の価値観「杜子春」
仙人に弟子入りした男が沈黙の行をする話。
二度大金持ちになった男がやった贅沢のきらびやかさだとか、沈黙の行のときに続く幻覚? のスケールのでかさだとか、とにかく描写が上手いです。
現実世界ではありえない展開も生々しく感じます。
朗読だけで想像がつくのすごいですね。
中国の古典に原作があるみたいですが、そちらも読んでみたくなりました。
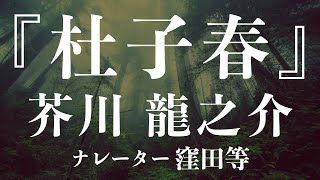
人を見た目で判断しているのに何かいい話っぽくなっている「蜜柑」
汽車に乗っているとき出会った小娘を観察する話。
序盤めちゃくちゃ人を見た目で判断しているのに、何となくいい話っぽく終わるのが理不尽ですね。少女の人間らしい優しい行いを見なければずっとそう思っていたんですか? となるし。
確かに人を見た目で判断してしまうことは起こりうるんですが、主人公自身の思想にちゃんとツッコミが入らないところが消化不良ですね。
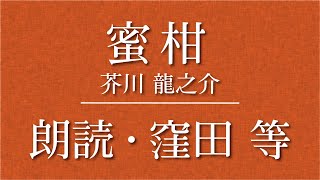
以上です。またまとめられる分量になったら記事を立てようかなと思います。









